ヘッドマッサージの勉強のコツ5選:学びを深めるインプット

いつもヘッドライフ通信をお読みいただき誠にありがとうございます。
ヘッドマッサージ資格講座・福岡代表の森脇です。
前回のコラムでは、『ヘッドマッサージの学びを深めるうえで効果的なアウトプット』というタイトルで、アウトプットの重要性について書きました。
知識をつけて(インプット)➡行動・共有(アウトプット)➡振り返り(フィードバック)➡インプット➡アウトプット・・・
この繰り返しが学びを深めるために大切だというお話でしたね。
そこで今回は、アウトプットの“前の段階”である『知識をつける(インプット=勉強)』という点にフォーカスしてみようと思います。
おすすめの方
☑ヘッドマッサージ・リラクゼーション施術初心者の方
☑当スクールの資格講座の卒業生の方
☑勉強のコツを知りたい方
☑知識をつけたいと考えている現役セラピストの方
☑セカンドキャリアとしてリラクゼーションに挑戦された方
上記に当てはまる方にとって、力になれる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。
※執筆者は医師ではなく、スクール講師として一般的な健康管理に役立つ情報を発信しております。 医学的な診断や治療は専門家への指導を受けてください。
※本記事は筆者の経験をもとに構成されていますので、参考程度にお読みください。

勉強なんて何年ぶり?勉強の仕方がわからない!
ヘッドマッサージ資格講座に限らず、当スクールを受講される方の殆どがリラクゼーション施術の未経験者です。
特に、セカンドキャリアとして受講される方の中には、『勉強なんて何年ぶりだろう』と声を漏らす方もいらっしゃいます。
日々の仕事や家事に追われ、何年も勉強や学ぶことから遠ざかっていたことから、『勉強の仕方がわからない!』という受講生は、年齢問わずいらっしゃいます。
ここからは、前回のコラムで紹介した
インプット ➡ アウトプット ➡ フィードバック
という形式をイメージしやすいように、“勉強”という言葉を“インプット”という言葉に置き換えて、そのコツを紹介していこうと思います。
インプット(勉強)のコツ1:教材は簡単なものを選ぶ
本来ヘッドマッサージセラピスト(以下ヘッドセラピスト)は、専門性のある知識をインプットして、お客様にもわかりやすいように専門用語を噛み砕くスキルが求められます。
しかし、現場経験の少ない初心者ヘッドセラピストにとって、それは少し難易度が高い傾向にあります。
そのため、ヘッドマッサージの教材を選ぶときは、いきなり専門書を選ぶのではなく、一般読者向けに作られている健康雑誌などがおすすめです。
一般向けに作られたものは、すでに簡単でわかりやすい言葉で書かれているため、スムーズにインプットできるからです。
ちなみに私は、初心者セラピストだった頃、『整体=ツボ』という偏った認識をしており、若さゆえの気合も相まって、ツボに関する分厚い専門書を購入したことがあります。
しかしながら、本の中身は当然専門用語だらけで、殆どインプットされずに終わったという苦い経験があります。
皆さんも気をつけてくださいね。
話を戻すと、教材を選ぶ時は自分知識量に見合ったものを選ぶことが大切です。
当たり前のことだと思うかもしれませんが、当スクールの講座を受講される勉強意欲の高い人は、ついつい難しい教材を選びがちです。
勉強意欲が高いことは良いことですが、簡単なことからコツコツと難易度を上げていく方が、インプットを継続させる観点からみても有意義であることが多いです。
インプット(勉強)のコツ2:多角的な視点で学ぶ
ヘッドマッサージ資格講座をはじめ、様々な講座で必ずお伝えしていることがあります。
それは『体の状態・不調の原因・施術の効果について断言しない』ということです。
いわゆる『診断行為』とみられるようなことは避けましょう、ということですね。
したがって、ヘッドセラピストがお客様に声をかける際は「○○の効果が“期待できます”」や「○○が原因“かもしれませんね”」という言い回しになります。
曖昧な表現だと感じる人もいるかもしれませんが、リラクゼーションの社会的なポジションを理解するためには必要な知識なので覚えておきましょう。
これらのことを理解したうえで、ヘッドセラピストのインプットについて考えると、より多角的な視点で学ぶことが大切だとわかります。
例えば「不眠」でお悩みの方がいるとします。
この時ヘッドセラピストは、お悩みについて断言することができない代わりに、“○○かもしれない”という可能性を、お客様に寄り添って一緒に考えることが大切です。(=傾聴と提案)
“○○かもしれない”という『知識のバリエーション』が多ければ多いほど、施術の組み立てや、原因の予想にも役立てることができます。
『知識のバリエーション』を増やすために必要なのが、多角的な視点ということです。
インプット(勉強)のコツ3:1つのことに注力しすぎない
ここでは前章でお伝えした『多角的な視点』をもう少し具体的にお話します。
前章の内容は、学びを深めるための“心得”だと思ってください。
多角的な視点で学ぶということは、『1つのことに注力しすぎない』と言い換えることもできます。
1つのことに注力すること自体は悪いことではありませんが、
- ヘッドマッサージ資格講座の受講生は頭(頭部・頭皮)のことだけインプットする
- 腸セラピー資格講座の受講生なら腸のことだけインプットする
といった短絡的な学び方では『知識のバリエーション』は増えません。
つまり、お客様のお悩みの解決に近づくための手段が限られるということです。
ここで具体例をあげてみます。 あなたが、緊張型頭痛(肩こり頭痛・首こり頭痛)でお悩みだったとします。
もし、あなたの目の前に、頭(頭部・頭皮)のことだけインプットしているヘッドセラピストと、肩こりなどの筋疲労についてもインプットしているヘッドセラピストがいたら、どちらにヘッドマッサージをお願いしますか?
もちろん後者ですよね。
『ヘッドマッサージセラピスト=頭皮マッサージの専門家』ですが、『頭皮マッサージの専門家=頭(頭部・頭皮)のことだけ知っている』では成り立たないのです。
1つのことに注力しすぎてしまうと、これに気づくことができません。
ヘッドセラピストなら、筋疲労に関する知識や、頭の疲れ(脳疲労)についてもインプットする必要があります。
少し大変そうに感じるかもしれませんが、“簡単なことからコツコツと”続けることが、学びを深めるに繋がります。
インプット(勉強)のコツ4:同じテーマの本を並行して2冊以上読む
ここで紹介するコツは、私の経験が色濃く出ているので、全ての人にマッチするかはわかりませんが、効果的なインプット方法だったので紹介します。
それは、同じテーマの本を並行して2冊以上読むことです。
※最近ではネットでインプットする人も多いと思いますが、ここでは本に限定してお話していきます。
(ネットでしかインプットしない人はネットに置き換えて読んでください)
例えば『自律神経』をテーマにした本、AとBがあったとします。
Aには「脳と腸は“副交感神経”で繋がっている」と書いてあり、 Bには「脳と腸は“迷走神経”で繋がっている」と書いてありました。
この2つの内容は、違うことが書かれているように見えて、実は同じことが別の言葉(表現)で書かれています。
本(情報)というのは、同じテーマだとしても著者の見解によって、言葉のニュアンスや、重点を置いている部分が違うものです。
前章の「多角的な視点」にも通じることですが、AとBを読んで、自分で考えた答え『C』を見出すことが、インプットにおいてもっとも重要だと私は考えています。
それはつまり、情報に振り回されずに、自分の頭で考える力をつけるということです。
ここでAしか読んでいなかったら、その力がつかないどころか、見解の違いにも気づくことができません。
いずれBを読むことがあったとしてもスピード感が違いますし、そのころにはAの見解が頭にへばりついて、Bの異なった見解に右往左往してしまうかもしれません。
2冊以上を並行して読むのはそれを防ぐためです。
このインプット方法は、私が初心者セラピストの頃から今も続けているおすすめの方法です。
近年ネットなどでよく目にする、極端かつ過剰な情報が流れてきても全く動じないのは、このインプット方法を続けているからだと思っています。
インプット(勉強)のコツ5:楽しく学ぶ
人間は、心が動いた出来事の方が記憶に残りやすいといわれています。
皆さんの人生で記憶に残っていることも、楽しかったこと・嬉しかったこと、または悲しかったことや、悔しかったことではないでしょうか。
これを踏まえると、ただ漠然とインプットを続けるよりも、楽しさを感じながらインプットした方が効果的といえます。
また、“楽しい・面白い”というプラスの感情が、脳を活性化させるという研究データも存在します。
これは、『自分の記憶力で授業についていけるだろうか』という不安を抱えた受講生にとって励みになるデータではないでしょうか。
『記憶力に自信がない』という声は、特に50代以上の方から多く聞かれ、他の受講生と一緒に学ぶことに不安を感じている方も多いです。
しかし上記のデータを見ると、記憶力の良し悪しではなく、“どれだけインプットを楽しむか” の方が重要といえそうです。
おさらい|学を深めるインプットのコツ
今回は、ヘッドマッサージセラピストのインプット(勉強)のコツを紹介しました。 内容をおさらいすると下記の通りです。
- コツ1:教材は簡単なものを選ぶ
- コツ2:多角的な視点で学び
- コツ3:1つのことに注力しすぎない
- コツ4:同じテーマの本を並行して2冊以上読む
- コツ5:楽しく学ぶ
改めてみると、『インプットのコツ(勉強)1~4』が『インプットのコツ(勉強)5:楽しく学ぶ』の方法として集約されていることがわかります。
インプットを楽しむためには、まず簡単なことから始め、ヘッドマッサージそのものだけでなく、関連する分野にも目を向けましょう(多角的な視点)。
同じテーマの本を並行して読むことで、自分の頭で考える力が身に付きます。
これらの過程で得られる気づきは、学びを深めると共に、ヘッドセラピストとしての人生をきっと豊かにしてくれるはずです。
最後に、何事にも言えることかもしれませんが、楽しくなければ続きません。
インプット(勉強)のコツを掴んで、楽しむことができたなら、ぜひ《インプット➡アウトプット➡フィードバック》という形式に落とし込んでみてください。
今回の内容が、皆さんのお役に立てば幸いです。
作成日:2020年11月20日
更新日:2025年08月31日
おすすめの記事
・ヘッド講師が初心者セラピスト時代に活用したおすすめの勉強教材!
・ドライヘッドスパの勉強をしたい!ドライヘッドスパを学ぶ人におすすめ
・【まとめ】ヘッドマッサージと浅層バックラインをあわせて学ぶメリット
※このページの内容は、一般的な情報と執筆者による経験をもとに作成しており、医療的アドバイスを提供するものではありません。健康に関する具体的なご相談については、専門の医療機関にご相談ください。また経済的な安定や増収増益、所得の増加を保証をする内容ではありません。
この記事の執筆者
森脇 ゆう

一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会
福岡代表講師
アクトエール整体学院 学長
NPO法人日本ストレッチング協会 認定ストレッチングインストラクター
福岡スクール会場
〒812-0036
福岡市博多区上呉服町14-26ルアパレス上呉服201号
森脇先生のおすすめ講座
・その他:初心者向け無料動画
ヘッドライフ代表よりコメント
福岡会場の森脇先生は、ヘッドマッサージ資格講座の講師でありながら、50代限定の整体スクールの学長も務める。
筋膜ラインを考えたボディケアマッサージやストレッチの専門家でもあり、福岡以外にも東京や大阪など出張講座を開催する全国で人気の講師です。
森脇先生が考案した「眠れる身体をつくるストレッチ講座(通称:ねむスト」も好評!
繋究力(けいきゅうりょく)を高める無料オンライン講座もおすすめです。
森脇先生の講演動画
森脇代表の整体スクール

この記事の監修・ページ作成者
江口征次
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家
Head Life(ヘッドライフ)代表
株式会社ヘッドクリック 代表取締役
リラクゼーションサロンの経営
・頭ほぐし専門店atama代表
・ヘッドスパ専門店atama代表
商品
・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売
・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売
登録商標
・頭ほぐし専門店atama 登録5576269
・頭ほぐし整体院 登録5977517
・骨相セラピー 登録5790990
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家として、2010年よりヘッドセラピスト養成講座を開始し、日本全国、海外からも受講がある人気ヘッドマッサージ資格講座を主催している。
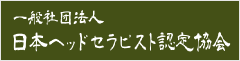

【登録商標】
頭ほぐし専門店atama 登録5576269
頭ほぐし整体院 登録5977517
骨相セラピー 登録5790990
※当サイト(ヘッドライフ)内の内容は、一般的な情報とサイト関係者による経験をもとに作成しており、医療的アドバイスを提供するものではありません。健康に関する具体的なご相談については、専門の医療機関にご相談ください。また経済的な安定や増収増益、所得の増加を保証をする内容ではありません。施術の効果など民間療法、伝統療法などの伝承に基づく内容となり、一部エビデンスがない情報もあります。当サイトの情報を利用する場合は個人責任となります。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
当サイトの掲載内容のすべては、株式会社ヘッドクリック代表取締役・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会理事長の江口征次が監修しています。
