
フットリフレクソロジー(足裏・足つぼマッサージ)がヘッドマッサージサロンにおすすめの理由
今回は、フットリフレクソロジーが、ヘッドマッサージサロンにおいてなぜ効果的なのか、おすすめの理由をご紹介します。
サロンメニューの幅を広げたい方や、お客様に新しい体験を届けたい方にとって、きっと参考になると思います。。
※執筆者は医師ではなく、スクール講師として一般的な健康管理に役立つ情報を発信しております。現時点で科学的に証明されてないものもあるため、医学的な診断や治療は医療機関等の専門家への指導を受けてください。

はじめにフットリフレクソロジーとは?
まずは簡単にフットリフレクソロジーとは何かについてお伝えします。
フットリフレクソロジーは、主に足裏に集まる反射区を刺激することで、全身の疲労回復や機能回復・改善を図る施術法です。
癒しのリラクゼーション効果に加え、冷えやむくみの改善、免疫機能や自然治癒力の向上もサポートできるため、多くのお客様に喜ばれる人気メニューです。

反射区とは
私たちの手や足には、体の臓器や器官の状態が「縮図のように映し出されている場所」があります。
この場所を「反射区(はんしゃく)」とよびます。
例えば、足の裏の一部が胃や腸とつながっていると考えられており、その部分(反射区)を刺激すると、対応する臓器の働きの活性化に繋がるといわれています。
つまり、足裏を揉むことは“全身の健康を整えるサポート”にもつながるのです。
リラックスしながら体調管理ができるのが、フットリフレクソロジーの大きな魅力です。
足裏(足底)マッサージ・足つぼマッサージ・フットリフレの違い

足(脚)を揉みほぐす施術は、フットリフレクソロジー以外にも足裏(足底)マッサージ・足つぼマッサージがあります。
似た言葉として使われますが、実際にはニュアンスや背景が少しずつ異なります。
整理すると以下のとおりです。
足裏(足底)マッサージ
|定義・特徴|
リラクゼーションサロンで最も多く使われる表現が「足裏マッサージ」です。
一般的には「足の裏をもむ・ほぐす施術」を指しますが、実際には足の甲や側面、さらには脛(すね)や脹脛(ふくらはぎ)といった下腿部までを含む場合もあります。
足裏のことを専門的に「足底(そくてい)」と表現することもあります。
ただし、「足つぼ」や「リフレクソロジー」のように明確な理論体系に基づくものではなく、多くの場合は専門的な理論にとらわれず幅広く使われているのが特徴です。
|目的|
・足の疲れの解消
・むくみの解消
・リラックス
☑ワンポイントアドバイス
足裏のアーチ(土踏まずなど)は、姿勢や歩行、全身のバランスを支える重要な部分です。
アーチが崩れると扁平足や外反母趾、膝・腰への負担、さらには首や肩の不調にもつながります。
足裏のアーチを整える整体や、距骨矯正といった方法を取り入れ、機能回復を目的とした足もみメニューを導入することで、サロンの技術レベルはワンランク上へと高まります。
足つぼマッサージ
|定義・特徴|
主に足裏にある“つぼ”を刺激して健康の維持や回復、体質改善を目的とする施術メニューです。
東洋医学的な考えに基づき、下腿から足先にかけての経絡(けいらく)やつぼ(経穴:けいけつ)を重視する方法であるため、専門的な知識が必要です。
|目的|
・不調に対応する「つぼ」を押して改善を図る
・疲労回復や機能改善
・体質改善
・リラックス
☑ワンポイントアドバイス
つぼ(経穴)の位置や押し方を覚えるのが苦手な方は、“点ではなく線でケアする”経絡マッサージ(トリートメント)がおすすめです。
さらに、オキシトシンやセロトニンの活性に役立つアロマオイルを併用することで、心身を深く癒すリラクゼーション効果が一層高まります。
経絡マッサージは、習得が比較的容易でありながら東洋医学の理論を取り入れることができるため、サロンメニューとしても人気が高く、導入しやすいワンランク上の施術法です。
フットリフレクソロジー(FOOT Reflexology)
|定義・特徴|
リフレクソロジーは、Reflex (反射)と logy (学問)をあわせた造語で「反射学」という意味です。
フットリフレクソロジーの反射とは、足にある“反射区”を刺激することで、全身の臓器や器官に働きかける足もみ健康法です。
アロマオイルを使ったリラクゼーション効果の高い英国式リフレクソロジーもあれば、刺激が強い台湾式、中国式もあります。
反射区を「ゾーン」とよぶこともあり、その場合は「ゾーンセラピー(足の反射区療法)」とよびます。
|目的|
・不調に対応する反射区を刺激して改善を図る
・疲労回復や内臓機能等の調整
・リラックス
☑ワンポイントアドバイス
やさしくほぐす英国式も人気ですが、日本におけるフットリフレクソロジーの大半は、台湾式や中国式を取り入れた「アジア式」が主流となっています。
国内では力強い刺激、いわゆる「強もみ」を好む傾向が強いため、お客様に満足していただくには、しっかりとほぐせる技術を身につけることが成功のカギとなるでしょう。
サロンオーナー視点:どの言葉を選ぶべきか?
リラクゼーションサロンの現状を見ると、実際にはフットリフレクソロジーを行っているのに、メニュー名は「足つぼ」と表示していたり、逆に足つぼマッサージなのに反射区図(足裏のイラスト)を使っているケースが見受けられます。
何故このようなことが起こるのでしょうか?
一見同じように思える「足裏マッサージ」「足つぼマッサージ」「フットリフレ」ですが、それぞれがもつ言葉のイメージやアプローチ方法が違うため、、サロンのメニュー化において、集客を考えた言葉選びが必要です。
☑足裏マッサージ
「足裏マッサージ」は専門用語に馴染みのない方でも理解しやすく、気軽に試してもらいやすい表現です。
実際の施術内容が「足つぼ」「フットリフレ」であっても、集客用のクーポンやPOPで「足裏マッサージ」と表現を変えることでサロン初心者やマッサージ経験が少ない層の利用率が上がる傾向があります。
☑足つぼマッサージ
東洋医学に関心のある方や、体質改善を求めるお客様には「足つぼ」という表現が響きます。
冷えやむくみで足が重だるい人で「強く押してほしい」「つぼをしっかり刺激されたい」という方や、健康志向の強い中高年層に人気です。
☑フットリフレクソロジー
反射区を表した図が印象的でお客様の目を引くアイキャッチとなり集客に繋がります。
また「リフレクソロジー」は専門的で上品な響きがあり、癒し重視のサロンや女性向けメニューに最適です。
美容クリームやアロマオイルを使用するなど、高級感を出したい場合にも有効です。
ターゲット層にあった言葉選び
お客様はメニュー名から施術内容をイメージします。
例えば、癒しを求める方には「リフレクソロジー」、強めの刺激を好む方には「足つぼ」、初心者には「足裏マッサージ」といったように、提供する施術内容とターゲット層に合わせて適切な言葉を選ぶことが、リピート率やサロンの信頼性を高めるポイントです。
ただし、反射区図を広告に使用しながらも、実際の施術はリフレクソロジーの理論やルールを無視した単なる足裏マッサージになるとギャップが生じて不信感につながります。
サロンオーナーは、「実際の施術」と「メニュー名や表現」の整合性の管理も必要です。
以上のように、足をもみほぐす施術には、いくつかの種類とそれぞれのイメージがあります。
いずれもリラクゼーション効果をもち、目的やアプローチの違いを理解して導入することで、メニューの幅と満足度を高めることができます。
おすすめ理由1:反射区を使い不調を整える!
リフレクソロジーの醍醐味は「反射区」を活用することです。
当スクールで学べるフットリフレクソロジーは、次のような反射区に対応しており、ヘッドマッサージで期待できる効果とも合致する部分が多く存在します。

反射区への刺激によって期待できる効果
以下、臓器や器官の主な役割と関連する不調例です。
心臓
役割:血液を体中に送り出すポンプの役割。大きさは拳よりやや大きく成人で約250~350g。
関連する不調例:心疾患、運動不足
腎臓
役割:血液中の老廃物をろ過して尿とともに排泄する。
関連する不調例:むくみ、高血圧、低血圧、関節炎、リウマチ、アトピー性皮膚炎
膀胱
役割:尿をためておく臓器。許容量は約500ml。
関連する不調例:むくみ、高血圧、低血圧、関節炎、リウマチ、アトピー性皮膚炎
前頭洞
役割:眉間の辺りにある副鼻腔のひとつ。鼻の中の乾燥を防ぐ。
関連する不調例:頭痛、不眠症、花粉症
鼻
役割:外気を取り込む際に、温度と湿度を与える。細菌やウイルスの感染を防ぐ(フィルター効果)。
関連する不調例:鼻のアレルギー、嗅覚異常
大脳
役割:精神活動、運動、感覚、言語や記憶などの中枢をなす。
関連する不調例:痴呆症、頭痛、不眠症、高血圧
脳下垂体
役割:ホルモンを分泌し、甲状腺・副腎・精巣・卵巣に働きかけ、機能を正常に保つ。
関連する不調例:発育不全、美容、乳房の発育、不妊症
三叉神経
役割:脳神経のひとつ。知覚神経で顔面の皮膚感覚と下顎の運動を支配する。
関連する不調例:顔面神経麻痺、片頭痛、不眠症
小脳
役割:平衡を保つ中枢。筋肉の運動を統合調整する役割。
関連する不調例:不眠症、高血圧、めまい
首(頸椎)
役割:重い頭を支え、複雑な運動を可能にする。
関連する不調例:肩こり、首こり、むちうち、寝違え
目
役割:光を感じ、物を見分ける。視神経を介して情報を大脳に伝える。
関連する不調例:目の疲れ、頭痛
耳
役割:外耳・中耳・内耳からなり、音を聞き取る。三半規管は平衡感覚を担う。
関連する不調例:耳鳴り、難聴、吐き気
甲状腺
役割:甲状腺ホルモンを分泌し、体温調節や代謝を促進。
関連する不調例:不整脈、バセドウ病、肥満、痩せすぎ
肩(僧帽筋)
役割:頸から肩、肩甲骨にかけての筋。肩こり筋とよばれる。
関連する不調例:肩こり、手の疲れ
呼吸器(肺)
役割:血液に酸素を取り込み二酸化炭素を排出。ガス交換を行う。
関連する不調例:肺炎、気管支ぜんそく、咳
副腎
役割:体内の塩分量調節と脈拍の調整。副腎皮質ホルモンを分泌し代謝やストレスの緩和を行う。
関連する不調例:ストレス
脾臓
役割:リンパ球を産生し、古くなった血液をろ過。
関連する不調例:貧血、抵抗力の低下
肝臓
役割:アルコールの分解、胆汁生成、栄養素の貯蔵や加工、血液量の調節など。
関連する不調例:アルコール性肝炎、栄養不良
胆のう
役割:肝臓で作られる胆汁を濃縮・貯蔵。脂肪の消化を促進。
関連する不調例:消化不良
胃
役割:食物を胃液と混ぜて攪拌し、殺菌・消化・一時的な貯蔵を行う。
関連する不調例:胃炎、胃潰瘍、嘔吐、消化不良
膵臓
役割:消化酵素(膵液)の生成。インスリンやグルカゴンを分泌し血糖値を調整。
関連する不調例:糖尿病
小腸
役割:食物を消化吸収。十二指腸・空腸・回腸の3部位からなる。
関連する不調例:下痢、低血圧、ガスによる膨満感
大腸
役割:水分を吸収し便を形成。盲腸、結腸、直腸から構成される。
関連する不調例:下痢、便秘、腰痛、痔
生殖腺
役割:男性は睾丸、女性は卵巣。ホルモンを分泌し発育や生殖に関与。
関連する不調例:発育不良、生理不順
胸椎
役割:12個の椎骨で構成され、内臓を保護。
関連する不調例:背中の痛み
腰椎
役割:5個の椎骨からなる。椎間板ヘルニアが多い部位。
関連する不調例:ぎっくり腰、腰痛症
仙骨
役割:5個の骨が融合して1つになる。仙骨神経の一部は直腸や肛門の感覚や運動に関係する。
関連する不調例:腰痛、坐骨神経痛
尾骨
役割:仙骨の先端の小さな骨。
関連する不調例:坐骨神経痛
肘
役割:上腕骨と橈骨・尺骨から成る関節。
関連する不調例:肘関節の痛み
膝
役割:大腿骨と脛骨、大腿骨と膝蓋骨から成る関節。
関連する不調例:膝関節の痛み
横隔膜
役割:胸腔と腹腔を分ける膜。呼吸運動を担う。
関連する不調例:しゃっくり、吐き気
胸腺
役割:胸部にあるリンパ器官。免疫に関与。
関連する不調例:風邪、呼吸器系の疾患
のど(声帯・咽頭)
役割:声帯は筋肉と靭帯から構成。咽頭には扁桃腺がある。
関連する不調例:のどの炎症、しゃがれ声
直腸
役割:大腸の一部。便をため排出する。
関連する不調例:便秘、痔
盲腸・虫垂
役割:小腸と大腸の結合部にある。虫垂はリンパ器官。
関連する不調例:虫垂炎
坐骨神経
役割:人体で最も太く長い末梢神経。腰椎と仙骨から出ている。
関連する不調例:坐骨神経痛、冷え性、足がつる
鼠径部
役割:左右大腿部の付け根。
関連する不調例:便秘、性欲減退、不感症
股関節
役割:体幹と下肢をつなぐ人体最大の関節。
関連する不調例:仙腸関節の痛み、坐骨神経痛
リフレクソロジーの反射区は全身にある複数の器官や臓器に対応しているため、自律神経・ホルモンバランスの調整を目的とするヘッドマッサージサロンのセットメニュー(相乗効果メニュー)としておすすめです。
リフレクソロジーには、手の反射区を使用するハンドリフレクソロジーもあります。
頭・手・足の末端から全身にアプローチするセットメニュー「末端療法(末端セラピー)」もおすすめです。
おすすめ理由2:頭と足はスッキリ感が得やすい!
頭は、肩こりや眼の疲れの影響で「重い」と感じやすい部位です。
一方、膝から下の脚や足裏は「冷え」「むくみ」「だるさ」を抱えやすい部位でもあります。
頭の疲れは、短時間の昼寝でスッキリした経験がある方も多いでしょう。
同じように、足の疲れは足湯に浸かるだけでも軽くなるのを感じたことがあると思います。
このように、頭のヘッドマッサージと足のフットリフレクソロジーは、施術後にスッキリ感を得やすい部位といえます。
特にフットリフレクソロジーは、施術後のスッキリ感やリフレッシュ効果を実感しやすく、世界中のマッサージ店で定番メニューとして広く取り入れられています。
当スクールのフットリフレクソロジー資格講座でも、施術のビフォーアフターを感じていただきやすい施術として好評です。
足(脚)が疲れる主な原因
脚や足が疲れる背景には、長時間の立ち仕事やデスクワークなどで座ったままの状態を続けることが原因に関係します。
ふくらはぎの筋肉は、血液やリンパを心臓へ押し戻すポンプの役割(筋ポンプ)を担っていますが、動きが少ないとその働きが弱まり、循環が滞りやすくなります。
その結果、足のむくみや重だるさを感じやすくなります。
また、重力の影響によって下半身には負担がかかりやすいことも要因の一つです。
座ったまま長時間過ごすと鼠径部(足の付け根)が圧迫され、血流やリンパの流れが妨げられる場合があります。
フットリフレクソロジーの際は、筋ポンプを回復させるふくらはぎマッサージや、全身の流れに関わる足の経絡マッサージも同時に行うことが理想です。
足(脚)の疲れが緊張型頭痛や頭皮のこりに
立っている時に片足に体重をかける癖や、座っている時に足を組む習慣などはありませんか?
いつも同じ側に体重をかける、足を組むことを続けていると、骨盤のバランスに影響を与えることがあります。
骨盤は上半身を支える土台でもあるため、ゆがみが生じると腰や背中の張り、肩こり、さらには頭重感(緊張型頭痛)、そして頭皮のこり(硬い頭皮)につながる場合もあります。
当スクールの講師陣が、ヘッドマッサージ講座の卒業生にフットリフレクソロジーをすすめるのはこういった理由があるからです。
頭皮と足裏のつながりをお客様に理解していただくには“お伝えするスキル”も必要ですが、「頭皮カチカチ」タイプのお客様には、是非フットリフレクソロジーやふくらはぎとのセットメニューをおすすめしてください。
一度理解して、効果を体感さえしていただければ、リピート率アップにつながることも期待できます。
おすすめ理由3:体験の幅が広がりリピート率アップ!

ヘッドマッサージでは「頭が軽い」「視界が明るくなる」「よく眠れる」といった体感を得る人が多いです。
一方で、フットリフレクソロジーは「重だるさが取れる」「むくみがスッキリする」といった即効性のあるビフォーアフターを感じやすい施術です。
両方を組み合わせることで体験(体感)の幅が広がり、お客様に「また受けたい」と思っていただけるサービスに成長させることができます。
飽きられるサロン・飽きられないサロン
何度かリピートしていたお客様がピタリと来なくなることがあります。
「前回も喜んでくれたのに何でだろ?飽きられたのかな?」と思っているセラピストさん、セットメニュー(相乗効果メニュー)のご案内を怠っていませんか?
いくらヘッドマッサージが上手でも「もっと良いサービス」を求めるのが消費者心理です。
その考えの中には、「新しい刺激」「新鮮さ」「希少性」などが含まれています。
これは人間の本能的な欲求の一つでもあるため仕方がありません。
飽きられないサロンでは、お客様の脳に多様な刺激(豊富なメニューでの新しい体験)を提供し、本能的な欲求を満たしています。
ここが、飽きのこないサロンとそうでないサロンの違いです。
特に、心身の不調を改善するのではなく、癒しやリラクゼーションを目的にご来店されるお客様は、「新しい刺激」「新鮮な感覚」「希少な体験」を求める傾向が強くなります。
一方で、不調改善を目的に利用されるお客様は、信頼できる施術者に一途に通い続ける傾向があります。
そういった意味で整体法が入った結果追求型ヘッドマッサージは、当スクールのウリでもあり強みになっています。
また、施術内容だけでなく、心身の健康や美容に役立つ情報やセルフケアのアドバイスをお伝えすることも、お客様の脳にとって価値ある刺激となります。
そのため当スクールでは、「お越しいただいたお客様に情報というお土産を渡す」ことを目的に、セロ活アドバイザー・睡眠ライフスタイルプランナー・頭皮毛髪アドバイザー・東洋医学アドバイザーなどの資格講座もおすすめしています。
ただし、眠りを与える程度の普通のリラクゼーションヘッドマッサージのサロンであっても、今回のテーマ、フットリフレクソロジーを含む相乗効果メニューを取り入れることで、「飽きのこないサロン」へと近づけることが可能です。
闇雲にメニューを増やすのではなく、サロンコンセプト・ターゲットにあったメニューの提供が前提にはなりますが、施術体感にバリエーションをプラスすることができればリピート率アップにも繋がります。
おすすめ理由4:癒しと同時に全身の調整が可能
フットリフレクソロジーは、足裏の反射区を刺激することで全身の調整(回復・改善)を目的とした施術です。
一方、ヘッドマッサージは、頭皮の筋膜リリース、脳への血流アップ、セロトニン活性、脳脊髄液の促進によって自律神経やホルモンバランスの調整、睡眠の質を高めることを目的としています。
どちらも全身の回復・改善をサポートする施術であり、目的が合致しているため、組み合わせることで高い相乗効果が期待できます。
フットリフレクソロジーとヘッドマッサージを組み合わせたセットメニューは、お客様の満足度を高めるだけでなく、安定した売上にもつながります。
サロン経営を支える柱の一つとして導入をおすすめします。
施術順はフットリフレが先、ヘッドマッサージは後
スクール受講者からはよく、「セットメニューでは、どの施術を先に行うのが良いですか?」という質問をいただきます。
そこでは、整体の考え方に基づく施術の順序と、フットリフレクソロジーを取り入れる場合のポイントについてお伝えします。
整体における基本の考え方
私が整体学校の学生時代に学んだ基本のルールのひとつに「大きな筋肉からほぐす」という考え方があります。
大きな筋肉は分厚い筋腹(きんぷく)をもち、それ自体が大きな“筋ポンプ”としての役割を果たしています。
施術では、まずこの大きな筋ポンプを回復させることで、まだほぐしていない末端の筋肉へも効率的に血液を届けられるようになります。
その結果、全身の血流が改善し、新鮮な酸素や栄養が隅々まで行き渡り、体を健康な状態へ導くことができるのです。
フットリフレクソロジーの場合
前述のとおり、フットリフレクソロジーは目・鼻・口・耳といった器官や、胃・すい臓・腎臓・肝臓などの内臓に対応する反射区を通じて、全身に働きかける施術です。
リフレクソロジーの大きな特長は、直接手で触れることのできない体の内部にアプローチできる点にあります。
反射区を使って身体の隅々を内側から活性化させた後、他の部位を施術することで施術効率が高まりやすくなるというのがリラクゼーションサロンにおける一般的な考え方です。
フットリフレとヘッドマッサージの場合
フットリフレクソロジーもヘッドマッサージも全身を内側から整える施術です。
この場合の施術順は、フットリフレクソロジーが先、ヘッドマッサージは後をおすすめしています。
<理由1>
フットリフレクソロジーを先に行うことで、足の重だるさが取れてスッキリした状態になり、その後のヘッドマッサージでは入眠のタイミングが早くなる傾向があります。
そもそも人は、靴や靴下を脱ぐだけでも解放感を覚え、気分がスッキリするものです。
そこに足をしっかりほぐす施術を加えることで、さらに深いリラックスへと導けます。
「足スッキリ」から「頭スッキリ」へとつなげるセットメニューは、「いつもより深く眠れた」と睡眠不足や不眠に悩む方から特に支持が高く、リピーター獲得にもつながる人気メニューとなります。
<理由2>
ヘッドマッサージサロンにおいては、お客様にできるだけ長く、質の高い眠りを体験していただくことが重要です。
そのため、先にヘッドマッサージを行って深いリラックス状態(爆睡)に導いた後でフットリフレクソロジーをはじめると、足への刺激で目が覚めてしまう可能性があります。
「せっかく気持ちよく眠れていたのに起こされてしまった」という不満を生まないためにも、施術順序はフットリフレクソロジーを先に、ヘッドマッサージを後に行うのが賢明です。
こうすることで、入眠しやすい流れをつくり、最後までぐっすり眠れる時間を確保できます。
<注意点>
フットリフレクソロジーは、足を清潔にしてから行うのが基本ですが、お客様の心理として「足裏を触った手で、そのまま頭部(髪・頭皮・顔)に触れられるのは抵抗がある」と感じる方も少なくありません。
そのため、フットリフレクソロジーの施術後は、一度手を洗いに施術スペースを離れることが望ましい対応です。
頭皮には健康維持に役立つ常在菌が存在しますが、不適切な菌が付着すると炎症などのトラブルにつながる可能性があります。
心理的にも「清潔=信頼」というイメージが強いため、衛生管理を徹底することはお客様の不安を和らげ、リラックス効果を高めるだけでなく、サロンのブランド価値やリピート率の向上にも直結します。
最後に:顧客ファーストで判断することが成功のカギ

今回は、フットリフレクソロジー(足裏・足つぼマッサージ)がヘッドマッサージサロンにおすすめの理由についてお伝えしました。
サロン運営において大切なのは、私たち施術者の都合や専門的なこだわりではなく、常に「お客様の立場」に立って考えることです。
どのメニュー名を選ぶか、どの施術を先に行うか、どのような言葉を使うか。
そのすべては「お客様がどう感じるか」を基準に判断することが、結果として信頼とリピートにつながります。
フットリフレクソロジーを導入する際も、リラクゼーション効果だけでなく、「清潔さ」「安心感」「新しい体験の提供」といった心理的な満足度を意識することが重要です。
顧客ファーストで判断を重ねていくことで、サロンは単なる施術の場ではなく、「また来たい」と思っていただける信頼の場へと成長していきます。
その積み重ねこそが、長く愛されるサロンづくりの最大の成功のカギとなるのです。
作成日
2025年08月18日

この記事の執筆者
江口征次
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家
Head Life(ヘッドライフ)代表
株式会社ヘッドクリック 代表取締役
頭ほぐし専門店atama代表
ヘッドスパ専門店atama代表
【商品】
・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売
・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売
【登録商標】
・頭ほぐし専門店atama 登録5576269
・頭ほぐし整体院 登録5977517
・骨相セラピー 登録5790990
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家として、2010年よりヘッドセラピスト養成講座を開始し、日本全国、海外からも受講がある人気ヘッドマッサージ資格講座を主催している。
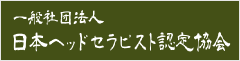

【登録商標】
頭ほぐし専門店atama 登録5576269
頭ほぐし整体院 登録5977517
骨相セラピー 登録5790990
※当サイト(ヘッドライフ)内の内容は、一般的な情報とサイト関係者による経験をもとに作成しており、医療的アドバイスを提供するものではありません。健康に関する具体的なご相談については、専門の医療機関にご相談ください。また経済的な安定や増収増益、所得の増加を保証をする内容ではありません。施術の効果など民間療法、伝統療法などの伝承に基づく内容となり、一部エビデンスがない情報もあります。当サイトの情報を利用する場合は個人責任となります。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
当サイトの掲載内容のすべては、株式会社ヘッドクリック代表取締役・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会理事長の江口征次が監修しています。
